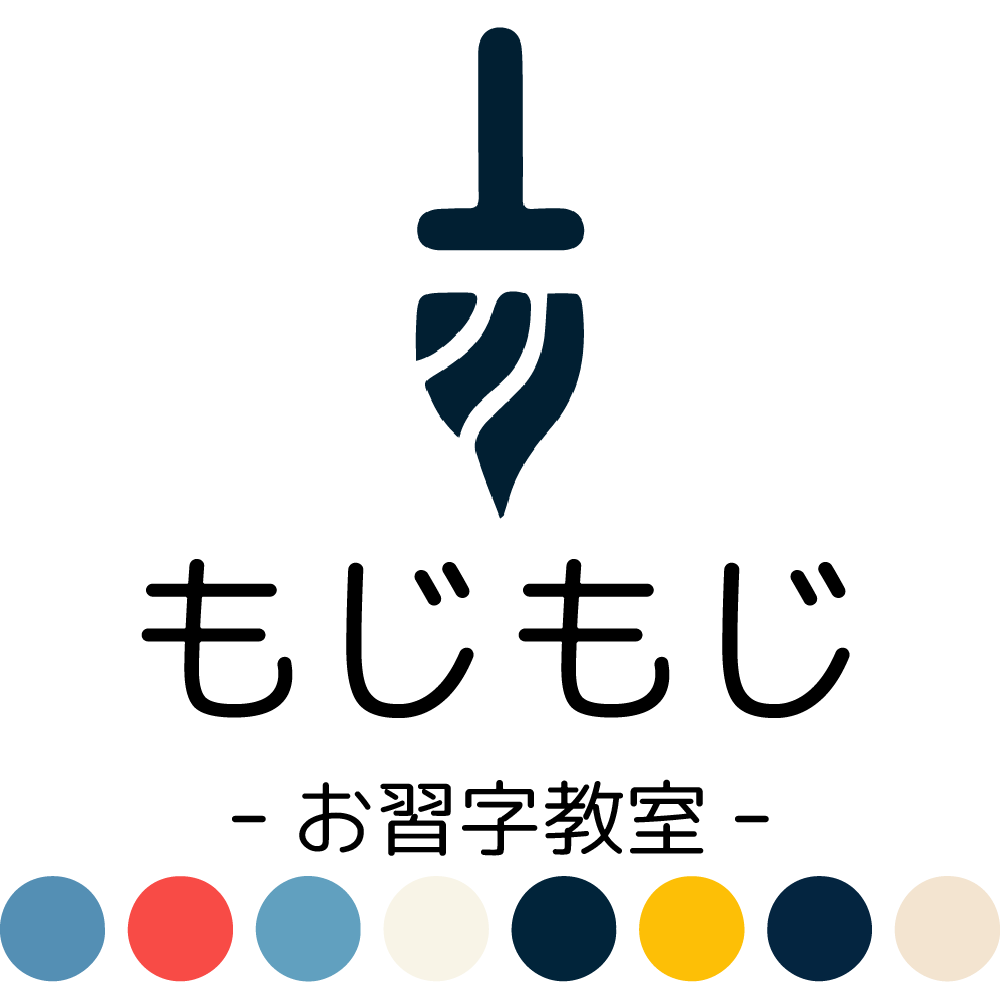こんにちは。上尾市のお習字教室✏︎もじもじのかどいです。
「漢字練習、なかなかきれいに書けてないな…」
「同じ字を何度も書いているけれど、ただ写しているだけに見える…」
子どもが取り組んでいる学校の宿題、そんな風に感じたことはありませんか?
私自身も子どもの宿題を見ていて、同じことを思った経験があります。
親としては「もう少し整えて書けたら」と願うけれど、つい小言になってしまいがちです。
もじもじでは、そうしたご家庭での“ちょっとした困りごと”を解決できるよう、工夫して教えています。
ただ繰り返すのではなく、「漢字はどんな意味をもってできたのか?」を一緒に確認しながら練習します。
理解してから書くと、一文字一文字に意識が向き、形も安定してきます。
実際に繰り返す回数は少なくても、考えて書く練習で身につくのです。
繰り返すだけでは身につかない?小学生の漢字練習
もじもじの硬筆練習では、各学年で新しく習う漢字を取り上げています。子どもたちは学校でも毎日のように漢字を練習していますが、ただ同じ字を繰り返すだけでは「形が崩れる」「意味を考えないまま書いてしまう」といったことが起こりやすいものです。
そこで、もじもじではまずその漢字の部首や成り立ちから説明します。たとえば「海」という字なら「水に関係するから“さんずい”がついているよ」と伝えると、子どもたちは納得しながら書き始めることができます。由来や意味を知ることで、形を正しく意識しやすくなるのです。
また、漢字だけを単独で練習するのではなく、平仮名と組み合わせて一文の中で練習します。そうすることで、漢字と平仮名の大きさや配置のバランスを自然に学ぶことができます。これは学校のノートや作文を書くときに、そのまま役立ちます。
繰り返しの数よりも「一度一度をていねいに、考えながら書くこと」。それがもじもじの硬筆練習の特徴です。
問いかけを重ねると、考えて書く力が育つ
「部首や意味を伝えながら練習している」と聞くと、子どもたちが次々に質問をして活気ある雰囲気を想像されるかもしれません。けれど実際はそういうわけではありません。子どもたちは最初から積極的に声を出すわけではなく、こちらから問いかけを続けていく形になります。
「この漢字の部首は何かな?」
「意味は何だと思う?」
「どうすれば整って見えるようになりそう?」
こうした質問を何度も繰り返していくと、少しずつ「考えながら書く」という姿勢が育っていきます。これは学年に関係なく、誰でも必ずできるようになることです。
また、もじもじでは何度も同じ字を繰り返すことはしません。その代わりに「一度ていねいに書く」ことを重視しています。そうすると、子どもたち自身も「ここが曲がっていた」「もう少し間をあけよう」と、自分の字を見直す力が育ちます。
この習慣がつくと、ただ「書き写す」から「自分の字を観察する」へと練習の質が変わります。短時間でも効果があるのは、そのためです。
宿題は同じでも、子どもの意識は変えられる
家庭での漢字練習は、どうしても同じ字を繰り返す形になりがちです。子どもにとっては単調に感じやすく、親にとっても「もっと丁寧に」と願うものの、なかなか思うようには進まないこともあります。
もじもじで硬筆の練習をしても、学校の宿題の内容が変わるわけではありません。変えられるとしたら、「漢字ってちょっと楽しいかも」という子どもの意識です。意味や成り立ちを知ってから書くと、ただの作業ではなくなるので、「もう一回やってみよう」という気持ちが少しずつ育っていきます。
そうなると、漢字を覚えることも、整えて書くことも、以前より前向きに取り組めるようになるかもしれません。学年に関係なく、そうした変化が起きるのを見られるのは、私にとってもうれしいことです。
『考えて一度書く』から始まる小さな変化
もじもじの硬筆練習は、ただ字をきれいにするためだけのものではありません。部首や成り立ちを知りながら、一度一度を考えて書く練習をすることで、子どもは「整えて書くってどういうことか」を少しずつ理解していきます。
同じ字を何十回も繰り返すのではなく、「考えて一度書く」を積み重ねる。その方法なら、学年に関係なく誰でも取り組むことができます。結果として、学校の宿題や作文の時間が大きく変わるわけではないけれど、「漢字ってちょっと楽しいかも」と感じられる子どもが増えること。それが、もじもじが目指していることです。
お子さんが漢字をどう受けとめるようになるか、そばで一緒に見守っていけたらうれしいです。

こんにちは!ブログにお越しくださりありがとうございます。
埼玉県上尾市で「もじもじ」というお習字教室を運営しています。
「うちの子、もっときれいな字を書けたらいいのにな」
「子どもの時期に、習い事で自信をつけさせてあげたい」
――そんな親御さんの思いに寄り添いたい。これが、私がこの教室を始めた理由のひとつです。
実は私、中学校の教員として子どもに教えていた経験があります。
子どもたちの書写の授業に携わる中で、字を思うように書けるようになる楽しさや、学びを通じて得られる喜びをもっと深く多くの子どもに伝えたいと思うようになりました。
特別才能があるわけではない私が、社会人になってから本格的に書道を学び始め、2025年で教室は12年目を迎えます。
教室のロゴに描いた色とりどりの◯は、それぞれ違う色を持つ子どもたちの個性を表しています。
一見同じように見えても、よく見ると違う。それは、子どもたち一人ひとりが持つ「その子らしさ」と同じです。
通ってくれる子どもたちが、学ぶことを楽しみながら成長していける場にしたい。
そのために、その子のペースを大切に、丁寧に、わかりやすく教えることを心がける。
ーー「もじもじ」は、習字を通して一人ひとりが自信を持ち輝ける教室を目指しています。
お習字のこと、お子さんのこと、どうぞお気軽にご相談ください!